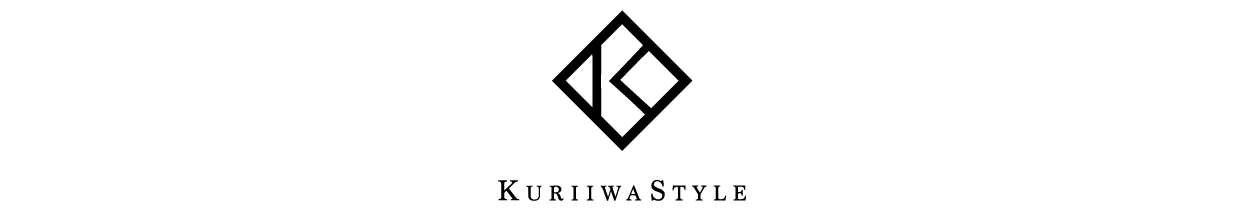2025/08/12 10:00

「50年経って初めてだよね、こういうの」「あ、そう、そうかな…?」
還暦を過ぎた姉の前にチョコレートパフェ、還暦目前の自分の前には、抹茶クリームあんみつ。
燦々と光が差し込む大きな窓から遠くに見える山並みと裾野に広がる広大な盆地が見える。
周りには家族連れや老夫婦、遠方からわざわざ来たと思われる女性同士や若いカップル。
その日、五つ歳の離れた姉が実家に到着するのを待ちわびていたかのように、
「あー、よかった。早く早く!予約してあるから。」「え、なに?」「とりあえず荷物置いて、ほら。」
ボカンと見つめる両親を残して靴を脱ぐこともなく、姉の車に乗り込んだ。
「ほら、いつも二人の世話ばっかりで疲れちゃうから、気分転換にね。」「え、なに?どこ?」
気温が40℃に迫る見慣れた町を眼下に白い軽自動車で急な上り坂を走らせながら姉が言った。
「ほら、だってさ、古民家みたいなところ好きでしょ。そこでカフェをやっているの。
そこに連れて行こうと思ったんだよね。眺めがすごく良いから。気分転換、気分転換。」
「え、なにそれ。そんなところあったっけ。」「少し前に出来たんだけど、美味しいんだよ。」
「へぇー、楽しみだ。」「ほら、あの山のあそこに見える赤い屋根、あそこまで行くよ。」
と、うれしそうに話す姉を横目に、話したことあったっけ、自分の夢みたいなことを、と思った。
若い頃、初めてのアルバイトとなった珈琲専門店で思い描いていた、山の中のコーヒー屋の夢。
デニムのエプロンにパイプをくわえたコーヒー屋のおじさんのイメージと、
太陽の光と火の熱だけで営業をするために、営業時間は日の出から日没までで、
店の真ん中には薪ストーブが焚かれていて、そこで温めたパンとスープと旨いコーヒー。
みたいなことを大きな大きな夢として思い描いていたことを、もちろん話していなかったし、
ログビルダーの見習いで山に入っていた頃、姉は銀行員として忙しく働いていたから、
話すことも交流することもなく、酒を飲まない姉とは酒を酌み交わすなんて、もちろんなかった。
五つも歳が離れているから一緒に遊ぶなんてことはまずなくて、
ガンダムを観て、ドラえもんとドカベンの漫画を読み漁る野球小僧だったし、
少し大きくなっても特に話すこともない、ひとり遊びの子供だったから、とても不思議だった。
唯一考えられるのは、毎月購読していた「山と溪谷」という月刊誌だけれど、それだって、
自分の部屋で読んでいたから伝わることもなく、とにかく不思議だったけれど、
まあ、これが姉弟、というものなのかな、と思ったし、気忙しい時間をぬってわざわざ、
山の中まで連れていこうとしてくれている姉の心情がうれしく、
週に一度の休日を月に一度は実家に行くという、割りとしんどい日曜日になっていた自分には、
たった数時間とはいえ、とてもありがたかったし、何よりも楽しみだった。
それにしても、50年以上一度も喫茶店でコーヒーとかパフェとかなかったかな、と考えてみた。
可能性が高そうな十代終わりには家を出ていたし、その後は自分へ東京、姉は地元だったから、
遊びに行くことなんてあるはすもなく、そもそも、あまり趣味というか、考え方も違ったから、
会うことも、会おうとも思わなかったし、唯一東京に研修で出張してきた姉を
不慣れな東京で宿泊先まで案内した時にしたって送り届けて終わりだったし、
帰省したらしたでずっと実家にいるか、温泉に行っているか飲みに行くか、だから全くなかった。
今こうして対面して座り、注文した子供のようなモノを目の前にしていることが初めてだった。
一緒に頼んだブレス式の深煎り珈琲を飲みながら、そういえば珈琲も飲まない人だったっけ、
と、改めて気がついたし、ポットサービスされた紅茶を飲みながら、「あー、苦くなっちゃった。」
そう言っている姉が身近に感じられ、何だか新鮮な心持ちで他愛もない話をして過ごした。
姉弟ってこんな感じなのかなと思ったその日にどうしても連れて来たかったそこは、
山の中腹にある古い洋館を改修して、木彫作家の父親の作品などを展示販売するギャラリーと、
郷土料理研究家の母親が作る食事や飲み物を提供する店を息子が切り盛りしていて、
雪深い冬期は休業、営業時間は夕暮れまで、というゆったりとした時間が流れ、
遮るものが一切ない崖っぷちに立ち、その眺望ははるか遠くに地元の山並みと河川が雄大に広がり、
その拓けた土地に田畑や町並みが広がり、背後の頂上まであとわずかの山に抱かれ、
とにかく素晴らしい場所にある、自分が思い描いていたカタチに近い素晴らしい店だった。
店の外に出て、火山岩らしき大きな岩に座り、暑いけれど清々しい青い空を眺めながら、
夢を持っていたけれど出来なかった「あの頃」を思い出していた。
到底実現など出来ないと諦めていた、想像や空想の範囲内を超えない夢物語だったし、
その方法もわからなかった若い頃、机上の空論のように山やログハウスの雑誌を読み、
あの頃流行っていた海辺の町の喫茶店を舞台にしたテレビドラマを観て、そうそうこの感じ、
海辺の町でも良いかも、などと妄想を膨らませていたあの頃から実際に海辺の町の生活を経て、
理想と現実と自分自身の実状に完全に諦めた「夢」からだいぶ時が流れて、銀座の片隅で酒場を持ち、
それを終えてまた、あの町に戻って生まれたばかりの酒場を預かっている今。
岩に寝転び見上げた青く高い空に、これから先、まだまだかも、と思えた。
午後になってますます暑くなった日差しを真正面から浴びる下り坂の車中で突然姉が言った。
「これからさ、少しずつこういうことをしていったら良いよね、今までなかった分…。」
「うん、そうだね」としか答えられなかったけれど、心から感謝していたし、
子供の頃には遠い存在、どちらかというと遠ざけていた姉との距離感が縮まった気がした。
明日からのお盆の期間、当時は家族で過ごして、父親の実家に行ったり、
朝4時に出発して新潟まで海水浴に行ったりしていたことも思い出した。
そこには確かに家族のカタチがあって、もちろん姉もいたし、一番小さい自分が真ん中にいて、
大騒ぎしていたんだろうと思うけれど、あまり覚えていないことが少し残念に思いながら、
この先何回姉とこうすることが出来るかわからないけれど出来るだけそうしたい、
そんな風に考えながら、実家で年老いた両親が待つ「家」に姉弟で向かった。
令和七年 山に抱かれて生きたことを思い出しながら
栗岩稔