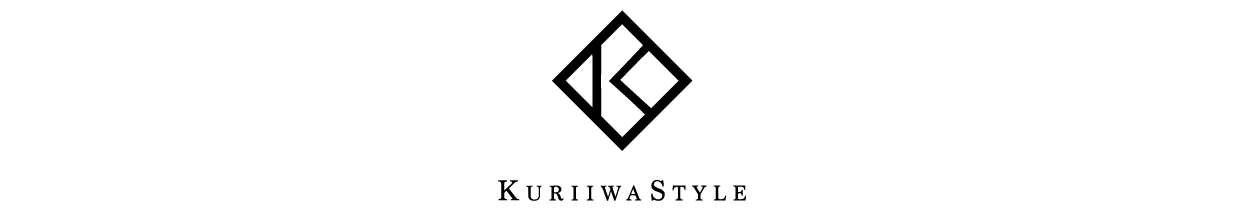2025/03/04 10:00

スティンガーという名のカクテル。
20世紀はじめにニューヨーク市のコロニーレストランのバーテンダーが考案したもので、
その後は店の名物カクテルになり、アメリカ都市部から世界に広がり、
もちろんここ日本でも100年以上経った今でも、クラシックスタンダードとして飲まれている。
けれど、新進気鋭のバーテンダーがいたりオリジナルカクテル重視の店が増えた今、
あまり飲まれることは多くないのかも、と少し寂しく思ったりしている。
そのコニャックの豊かな味わいとミントリキュールの爽やかな味が混ざりあい、
さわやかな甘味が口いっぱいに広がる少し強めのショートカクテルで、
味わいはもちろん、背景にあるものもあわせて好きなカクテルのひとつになっている。
酒場の景色だったり、繰り広げられる物語のようなものが好きなのかもしれない。
例えば小説で言うと、大好きな英国の推理小説の枠を超えた文学を著す作家、
ジョン・ル・カレの「寒い国から帰ってきたスパイ(邦題)」や、
イアン・フレミングの「007ダイヤモンドは永遠に(邦題)」で象徴的に使われ、
映画では、007シリーズのいくつかの作品ではもちろんのこと、
グレース・ケリー、ジーン・ケリー、ルイ・アームストロングなどが出演する映画、
「上流社会(邦題)」のホームバーのシーンで作られるカクテルがそれだったり、
ジャック・レモン主演「アパートの鍵貸します(邦題)」では女性を口説く時にと、
さまざまな場面で使われているカクテルのひとつになっていて、
印象に残っているし、実体験としとも忘れられない物陰(!?)がある。
鎌倉で小さな酒場を預かっていたある日、まだ少しだけ肌寒さが残る春先、
その美しい女性が海風と一緒に扉を開けてカウンターに座った。
そのオーダーが「スティンガー」で、その佇まいと所作が美しく、
夕暮れ間近の人が少ない酒場の美しい景色につい見とれるほどの時間だった。
一杯だけ飲むと「ありがとう」と、ひと言残して帰っていく、
そんなことが週に一度、二週間だけ、だから二回だけのスティンガーの時間。
そもそも、スティンガーという言葉は、昆虫や植物の針を意味していて、
それが転じて、風刺や皮肉を言う人にも使われたりするけれど、
そのスティンガーは針、特に微毒を持った毒針だと感じられるような美しい景色だった。
その姿を見ることなく終わろうとしていた三週目の終わり、閉店後の酒場の電話がなった。
「こんばんは。突然ごめんなさい。無理なお願いかもしれないけれど…。」
「え、何でしょう…。」と答えながらも、これから店に来たいのかな、
もう閉めちゃったな、残念だけど…、と頭のなかでぐるぐる考えを巡らせながら待った。
「次の月曜日っておやすみでしょ、午後三時に横浜のシェラトンホテルのシガーラウンジ、
ご一緒出来たらなと思って、無理なお願いかもしれないけれど…。良いかしら。」
と思いもよらない言葉に「はい、お供します。」と気の効いた言葉も言えず、
「ありがとう」の言葉で電話を終えたものの、受話器を握りしめたまましばらく、
全ての時間が止まったかのように固まっている自分がそこにいた。
緊張しながら期待しながらバタバタしながら終えた日曜日の深夜、
翌日のことを考えると久しぶりに心地好い疲労感いっばいで酒場の一週間を終えた。
月曜日午後二時半、子供の頃から刷り込まれて癖が抜けない約束の十五分前行動と、
いても経ってもいられない動揺と期待の十五分で三十分も前に到着した横浜駅。
駅から直接入ることが出来る歩道橋、少しだけ春めいてきた夕暮れ前の光のなかで、
早すぎた到着に更に焦りを深め、自分の居場所を探そうとしていた矢先、その女性がそこいた。
「あ、やっぱり」と微笑みながら自然に腕を組んで歩き出し、バーラウンジに向かった。
いつものようにジンリッキーと対面にはコニャックソーダ、
女性が選んだ葉巻のサイズと香りを見極めた自分の葉巻、そうして豊かな時間が始まった。
それぞれの葉巻の香りを纏いながら、半分近くになった頃には、
ネグローニといつものスティンガーが並び、二つの時間が調和、
共有した時間と酒と葉巻とすべてを終えた午後五時。
日が長くなりかけの夕暮れ迫る歩道橋で終わった豊かな時間。
後ろ髪を引かれながらも満足で充足した余韻に包まれながら歩き出し、
ふと潮風が懐かしく、鎌倉に気持ちが向かったその時に背後に迫る早足のヒールの音。
振り向くとそこにはその人がいて、何も言わずにハグをした少しの時間。
「ありがとう」「こちらこそ」の二言だけでその豊かで美しい一日を終えた。
満ち足りた、二度とないと知っている時間の終わりを横須賀線車内でひとり感じ、
自然と溢れる笑顔を止めもせず、二つの葉巻の香りと彼女の残り香を閉じ込めるように、
スプリングコートの襟を立て、座ることなく窓の外を流れていく景色を眺めた。
すべてに満ち足りたその日の夜は一滴の酒も飲まずに一日を終えた。
あの美しい女性との「物語」はちょうど今頃、この季節だった。
まだ桜の蕾が色づきもしないけれど、少しだけ緩んでいて、
柳の新芽が少しだけ膨らみはじめたこの季節だったとはっきり覚えている。
もちろん、東京と横浜の街の光の色は違うけれど、ちょうど今だった。
その年の桜が咲いたある日、唯一交換していたメールアドレス、
やり取りすることは避けていたメールアドレスから一編の美しい俳句が届いた。
けれど、それ以上でもそれ以下でもなく、ただ桜の花についての一句。
返句したメールには「ありがとう」とひと言で終えたきり、今まで一度も音信はない。
けれどそれで良い、あの美しいスティンガーの記憶げあれば、それが良い。
令和七年 梅香る桃の節句に桜について徒然と
栗岩稔