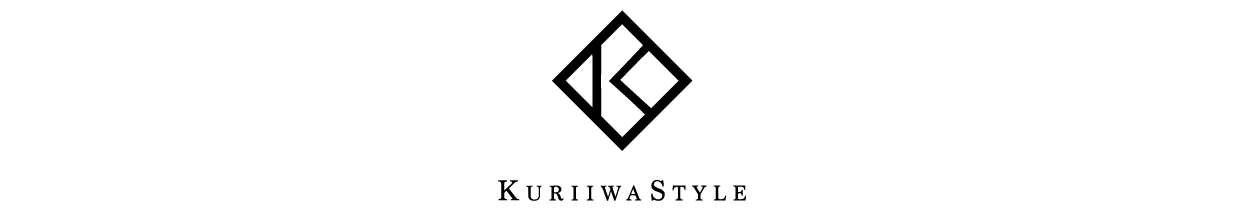2024/08/13 10:00

街では蝉が鳴き納めのように大合唱している。
自宅のラジオでは夏の全国高校野球の中継をしている。
100年目を迎えた甲子園球場で106回目の熱戦の火蓋が落とされた。
開会式後の始球式では、江川卓さんが投げたらしい。
あの人が作新学院で怪物と言われながら、敗れた試合は見ていない。
江川卓といえば、どちらかというと背番号30の巨人のエースという印象が強い。
自分にとっての甲子園は小学生の頃に食い入るように観ていた、
和歌山県代表箕島高校と石川県代表星稜高校の延長18回の熱戦、
フルスイングでまさにかっ飛ばすやまびこ打線の池田高校、
同世代の彼らが輝いて見えた、次元の違うPL学園の清原と桑田、
そのPL学園が池田高校を下して新たな時代のはじまりを感じたあの試合、
すべてが金属バットのかん高い打球音と大歓声、ともに戦う大応援団、
自宅の庭では蝉の大合唱と、そんな夏を思い出す。
けれど、懐かしくやさしく楽しい夏の思い出とは言えない。
夏休みといえば、サザエさんのカツオのように苦手な宿題、
カナヅチなのにほとんど毎日、行かなければいけない水泳教室、
友だちと遊ぶことのなかった、短いけれど長く感じた夏休み。
野球でいえば、レギュラーになることなく終えた中学校の野球部の最後の夏。
長野県独自らしい、お盆が終わると夏休みが終わる短い期間と、
すぐに感じる秋の気配のなかでも続く、冷たいプールでの水泳授業。
夏休みの思い出というよりも、夏のほろ苦い記憶ばかりを思い出す。
もうひとつ、どうしても忘れられない記憶は1985年8月12日の日航機墜落事故。
高校の夏休みが終わる頃に固唾を飲んで、テレビの前で固まり、
状況が全くわからないままの中継を無言で観ていたあの日は、
遊びに来ていた親戚のおばさん(今考えればいとこ)がいて、
お茶やお茶菓子が並び、すいかもあったけれど、誰も手を伸ばすことなく、
誰も話すことなく、長野県か群馬県か県境か行方すらわからず、
静かに時間が流れる、あの緊張した空気感は今でも覚えている。
庭では変わらず蝉の大合唱だったことも鮮明に甦ってくる。
時期的にも増える、広島や長崎、終戦の日のことが吹き飛ぶような、
テレビの向こうだけれど、すぐ近くの山で悲しい結末を迎えたあの日。
その太平洋戦争の話についても、
昭和ヒトケタ生まれの両親はあえて触れないようにしていると感じ、
いつもに増して重苦しく切なく、モヤモヤした疑問が残ったあの夏。
今にしてみれば、あの日を境に報道や残された歴史よりも、
事実に対して自らが調べて自分なりの考えを持つようになった、そう思えるあの夏。
海無し県のプール遊び、山に入ってカブトムシ採り、縁側ですいか、夜には花火、
そんな夏の定番のような楽しい思い出があまりなく、思い浮かばない、
少しほろ苦い、というより苦手だった夏の記憶。
先日、大きな大きなすいかを丸々一個いただいた。
何十年ぶりかにかぶり付いたすいかがとても美味しく、ありがたくいただいた。
けれど残った皮や匂いにふと、あの夏の記憶が甦って切なくなった。
けれどやっぱり、そのすいかはすこぶる旨く、あっという間になくなった、
その食べ終えた時のうれしさに楽しかった夏休みの記憶を思い出した。
子供の頃は毎年、夏休みに父親の実家に帰省することが我が家の年中行事だった。
先祖の墓参りと仏壇前の大広間に集まる親戚一同の
少しわかりくい方言混じりの会話が響き、大人は酒を酌み交わし、
子供たちはご馳走をたらふく食べて、山に遊びに行く。
カブトムシを探し、オニヤンマを追いかけ、喉が乾いたら、
畑の完熟すいかをその場で食べ、おやつにはきゅうりとトマト。
あの味が忘れ難く、たまらなくおいしかった大人になるまでの夏の記憶。
そんなやさしい記憶を思い起こした、今年のすいかに感謝した。
だいぶ歳を重ねてから、一人きりの年中行事がある。
上京以来年数を経て始まったそれは、小津安二郎監督「東京物語」を観ること。
観るたびに感じかたが変わるその作品、今年は特に身に染みる、
そんな気がするけれど、とにかく観ないと夏が終わらないし、
秋もはじまらないし、自分自身も節目を迎えられない。
だから今年も観る。来年以降の東京物語はどうなるだろうと思いながら。
この夏、大きなすいかひとつでいろいろなことを思い出し、気づかされた。
たかがすいか、されどすいか。夏といえば、蝉と甲子園とすいかかと。
そういえば、サザンオールスターズのアルバムにもありましたね。
自分が上京した頃でしたかね「すいか」が発売されたのは。
60曲ぐらい詰め込んだかサザンオールスターズ前期のベスト盤、あれはよかったなー。
大人と子供の境目の頃の、どこか違うところがムズムズしたり、
ざわついたり、うれしかったり、恥ずかしかったり、切なく思ったり…。
いずれにしても、すいか、です。
令和六年 秋の気配ゼロの立秋を過ぎた東京で
栗岩稔