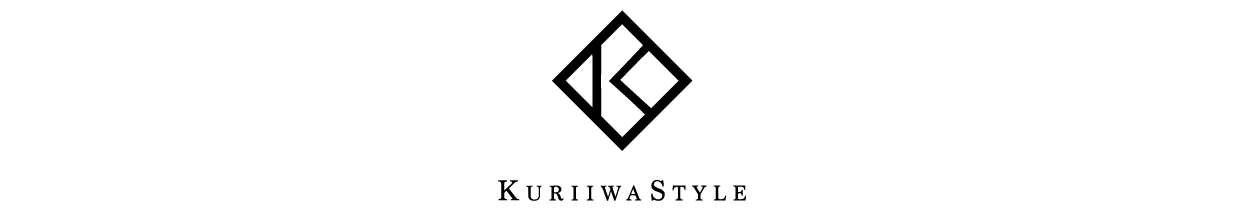2023/07/04 10:00
 重松清著「いとしのヒナゴン」を読んだ。
重松清著「いとしのヒナゴン」を読んだ。
山間の町で目撃された正体不明の生物
「ヒナゴン」を基に繰り広げられる物語。
「ヒナゴン」が初めて目撃されたのは
戦後復興も落ち着いた頃のこと、
相次いだ目撃情報に町が盛り上がり、
行政、メディアも巻き込んで、
町の経済も活性化し、町自体が元気になっていく。
そして、ひとつの情報が元で
興醒めしていった「ヒナゴン」。
町民同士の信頼関係すら希薄に
なっていってしまう。
バブル経済を過ぎて、
産業の空洞化が進み、高齢化が進み、
不安定さが増す行政運営のなかで沸き起こる、
国が推進する市町村合併。
そして、町はさらに町民同士で二分化されていく。
かつての「ヒナゴン」を探して
山中に分け入った悪ガキたち。
大人になった彼らのなかのガキ大将で
元暴走族で元ヤンキーのイッチャン。
自分の生きる町のために
町長選挙に立候補して勝った元悪ガキの町長。
彼は「ヒナゴン」を信じて町のための
「何か」を求めて勝負に出る。
新町長が創設したヒナゴンのための「類人猿課」。
そこに関わることになった元同級生の3人。
東京から逃げ帰ったノブ、
都内有名大学卒業後に合併のために戻った西野、
地元に残り小学校教諭として
町のことを考えるジュンペ。
この3人の今の若者が目にする
現実と町の未来、彼らの人生とは。
この本を読み終えたら故郷の山を見たくなった。
だから行った。行ってすぐ帰ってきた。
寂しさだけが残った。
どうしても自分自身を確かめたくて
行きたくなった自家焙煎珈琲の店。
あの頃、その景色に憧れて
美味しい珈琲を飲みたくて、
時間があれば、というより時間を作って行っていた。
まだあることを期待しながら、
飲食店が密集する小さな繁華街を歩いた。
シャッター街になったかつての目抜通りの
一本裏の路地を彷徨った。
夕暮れ迫る路地のさらに
裏側で斜陽に照らされた看板を見つけた。
薄暗い店内に明かりが灯っていることに安心した。
扉を開けたら変わらないドアベルの鈍い金属音がした。
「いらっしゃい」
「アイスコーヒーをください」
「あれ、お客さんは昔…」
「今日35年ぶりに来ました。
お元気そうで何よりです」
「まあね…、なんとかもってますよ…」
そう言いながら曲がった腰をさすりながら歩く。
お気に入りだった窓際の席に
座り懐かしさとともに店内を見渡す。
40年以上そこにある店の
40年分のくすみに気づいた頃、
35年前と変わらない
銅製のカップを満たしたアイスコーヒが出される。
鼻腔に広がる豊潤な薫り、口内に広がるそのうまさ。
苦味、酸味、甘味のバランスが絶妙に交わる味わい。
自分自身で目指した味わいの
アイスコーヒーが美味しくて安心した。
けれど、変わらないことの良さのための
何かが足りなくて寂しかった。
時代に倣った外の灰皿でタバコを吸う。
煙の向こうに広がる人の
気配が全く感じられない路地。
開店前の活気が感じられない、
たくさんあるはずの飲食店。
以前はなかったはずの深夜に輝く
風俗系のけばけばしい案内所。
いつになく煙が目に染みる一服だった。
店内に戻り、名残惜しい味わいの珈琲を飲み干した。
「ありがとうございます。ごちそうさまです」
と誰も見えない店内に声をかける。
「はい、はい」
と店の奥の客席から立ち上がるマスター。
「500円ね、ありがとう。また、寄って」
「ありがとうございます。お元気で」
決して、ではまた、と
言えない気持ちに押し出されながら、
自身の店の参考にした
大きな大きな一枚板の回転扉を押した。
金曜の夕暮れの寂れた通りから
冷たいシャッターが目立つ坂を
足早に、転がるように、
昔はなかった新幹線駅に下っていった。
ふと、真っ白できれいな暖簾が
風に揺れる店が目についた。
その老舗うどん屋に懐かしさと
不安を覚えながら暖簾を押した。
腰が曲がった女将が元気に迎えてくれたきれいな店内で、
よく冷えた生ビールと地元ならではの馬肉の肉うどんをいただいた。
変わらず美味しく、懐かしい味がした。
けれどやっぱり、寂しかった。
滞在時間約3時間の故郷の小さな町への小さな旅、
大きかったはずの故郷の山が何だか小さく見えた。
令和五年 憧れの美味しい珈琲を飲みながら。
栗岩稔