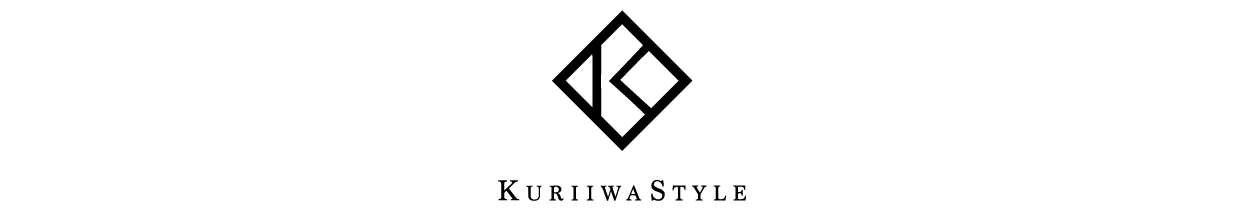2022/10/11 10:00
 その瞬間は突然訪れた。
その瞬間は突然訪れた。
海辺の町の酒場の開業前、
まだ冷たさが残る海風が流れ込む。
開け放たれた昭和初期のままのガラス戸。
そこに現れたのは、
日本に数頭しかいないはずの、スレンダーな茶色の狩猟犬。
そして、春の陽光を避けていたサングラスを頭に乗せ、
海風に乱れる長い黒髪を押さえたスレンダーな美しすぎる女性。
「ごめんなさい、お忙しいところ。いつからですか?バーですよね?」
「えっ、あ、はい。4月29日からです」
「もうすぐですね、楽しみにしています。ありがとうございます」
「え、あ、はい、こちらこそ……」
と的外れな答え。
美しいドイツの狩猟犬に引きずられるように立ち去る背中を茫然と見送る。
手が止まり、足が止まる、キラキラ光る、春の午後。
酒場の時間が動き出し、多忙を極めた緊張と疲労と反省の日々。
閉店後、すべてを終えたカウンターに独りで一杯だけの時間。
ふと思い出すのは、あの開け放たれたガラス戸の美しい景色。
淡い期待を打ち消す努力のために、少し強めのジン・リッキー。
開け放たれたガラス戸から流れ込む海風に潮の香りが混じる頃、
その瞬間は突然訪れた。
爽やかに美しくサマードレスをそよがせながら現れた。
消し去っていた淡い期待が喜びに変わり、久しぶりにドキドキした。
「こんばんは。二人ですが、入れますか?」
「あ、おふたり、ですね。あ、こんばんは。こちらへどうぞ」
カウンターに一番近い二人掛けのベンチソファに座る、
美しい女性と海辺の歴史ある町の爽やかな男性。
束の間の喜びが落胆に変わった、夏のはじまりの夕暮れ。
夜風すら生温くなった真夏の夜、酒場の電話が鳴った。
「今からひとりで行きたいんですが、お席は空いていますか?」
「ありがとうございます。カウンター席が空いていますので、どうぞ」
「ありがとうございます。5分ぐらいで行きますね」
「お待ちしております」
と同時に新品のコースターを一番奥の席に置く。
名前すら聞かなかったその声に、聞き覚えを感じながらも仕事に戻る。
5分後に訪れたその時、
普段は使うことのない言葉がつい洩れ出す。
「今日はおひとりなんですね」
「あ、あの人ね。彼は隣に住んでる幼馴染みなんです」
「え、あ、そうでしたか」
冷静さを取り繕いながら酒を作る、熱すぎた真夏の夜。
今でもはっきり覚えている、
デュボネをオンザロックでレモンを少し。
その景色と白くて丸いコースターともに。
多忙過ぎて記憶にすら残らない夏が過ぎ、
風向きが変わり、夕陽射し込むガラス戸にその人は現れた。
電話もなく、あの夏以来、ひとりでまた。
「こんばんは。どうぞこちらへ」
「ありがとうございます。前と同じ席ですね、良かった」
コースターを置きながら、同じ酒の準備をする。
「そういえば、名前を伺ってなかったなと思って…。伺っても良いですか?」
「そういえば、そうでしたね」
と差し出す名刺。
「ありがとうございます。ペンをお借り出来て?」
「え、あ、どうぞ、こちらで」
と渡す、長年愛用しているクロスのペン。
デュボネオンザロックが乗る前のコースターを裏返し、
名前と連絡先を書いて元に戻す。
「今日、私の誕生日なんです」
「え、私も、です……」
個人的な想いでコースターのメモをもらったのは、
最初で最後、だったかな……。
この続きは、またいつか。
令和四年 神無月に紙に感謝したあの日
栗岩稔